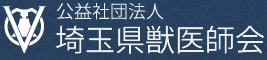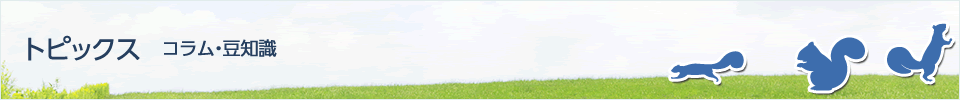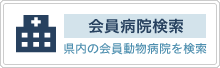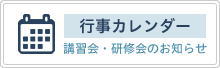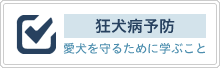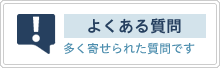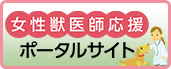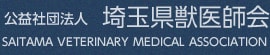近年、国内で高病原性鳥インフルエンザ(以下「HPAI」)や豚熱といった家畜の伝染病の発生が続いています。こうした伝染病が発生した場合、まん延を防止するために感染個体が確認された農場で飼育されている鶏や豚は全て殺処分されます。
国内の農場における発生状況について、HPAIは2024年シーズン(2024年10月以降)に14道県で51事例、豚熱は2024年度に6県で7事例の発生があり、鶏などの家きん約932万羽、豚約5万3千頭が殺処分されました。
家畜の伝染病がまん延してしまうと、私たちの生活にどのような影響が生じてしまうのでしょうか。殺処分によって鶏や豚の飼育頭数が減ってしまえば、鶏卵や肉の供給量が減ることとなり、鶏卵や肉など畜産物の価格が上昇してしまいます。
令和4年度には全国でHPAIの発生が多発し、国内で飼育される採卵鶏の約10%以上が殺処分され、鶏卵価格が高騰してエッグショックという言葉が使われるようになりました。その後、令和5年度にはHPAIが発生した農場での生産が回復したことなどにより鶏卵価格は下降しました。しかし、令和6年度は猛暑の影響による供給量の減少や1月にHPAIが頻発したことにより、例年より価格が高い状況となっています。
豚肉については、豚熱ワクチンを豚に接種してることもあり、HPAIのように全国的な発生が起きていないため、はっきりした価格上昇は起こっていません。
しかし、海外に目を向けると、中国ではアフリカ豚熱という伝染病が発生したことにより、豚肉価格が高騰したことがあります。現在中国は4億頭以上の豚を飼育する世界一の養豚大国ですが、2018年にはアフリカ豚熱の感染が拡大したことにより、中国国内で飼育される豚の頭数が約40%減少しました。この結果、2018年8月には1kgあたり約20元(約318円)だった中国国内の豚肉価格は、2019年2月には1kgあたり約50元(約795円)と約2.5倍にまで跳ね上がりました(出典:農畜産業振興機構「中国の養豚業におけるアフリカ豚熱の影響」)。
幸いなことに、これまでアフリカ豚熱は日本国内では発生していませんが、中国や韓国をはじめとしたアジアのほぼ全域、そしてヨーロッパやアフリカの広範囲で発生が確認されており、昨今の物流の発達や訪日外国人の増加を背景に、国内にウイルスが侵入するリスクは高くなっています。加えて、アフリカ豚熱は豚熱のように有効なワクチンが開発されていないため、ひとたび国内で発生するとまん延を食い止めるのは容易ではないことが予想されます。
こうした家畜の伝染病の発生を防ぐため、私たちには何ができるでしょうか。家畜を飼育する畜産農家では、伝染病の原因となるウイルスなどを農場内に侵入させないため、野生動物の侵入を防ぐための柵を農場周囲に設置したり、農場内で使用する長靴を鶏舎や豚舎ごとに履き替えるなど、様々な対策を行っています。ウイルスなどを農場に侵入させない、また、もし農場で発生した場合に伝染病を周囲へ広げないため、以下の点に御協力くださるようお願いします。
(1)野生動物にはむやみに近づかない
HPAIは野鳥にも感染するため、極力、野鳥には近づかないようにしてください。毎年、初冬になるとハクチョウが北方から飛来したことがニュースになりますが、HPAIウイルスはシベリアやアラスカから飛来する渡り鳥によって国内へ運ばれるといわれています。ハクチョウなどが飛来した水場の周辺にはウイルスが存在する可能性が高いため、決して近づかず、餌やりなどは行わないようにしてください。
一方、豚熱は野生のイノシシにも感染する伝染病で、現在、国内の広い範囲でイノシシの感染が確認されています。特に、イノシシの死体を発見した場合、死因が豚熱である可能性を否定できません。
ウイルスを拡げないために、もし野鳥や野生動物の死体を見つけても決して近づかないようにしてください。
なお、死亡イノシシについては状況によって豚熱の検査を実施するので、死体を発見した際はお近くの環境管理事務所又は市町村に連絡をお願いします。また、死亡野鳥については、環境省が設定する「対応レベル」と「検査優先種(野鳥の種類)」に応じて高病原性鳥インフルエンザの検査を実施します。同じ場所で怪我のない野鳥が複数羽死亡している場合や、怪我のない水鳥(カモ、ガン、ハクチョウ、カイツブリ等)又は怪我のない猛禽類(ワシ、タカ、ハヤブサ、フクロウ等)が死亡している場合は、お近くの環境管理事務所に連絡をお願いします。
(2)靴に付いた泥は山で落とす
感染したイノシシから糞などと一緒に排出されたウイルスは、他の野生動物に付着して運ばれるなどして土にも存在しています。レジャーなどで山間部などイノシシの生息地域に行かれた際は、帰路につく前に靴に着いた泥をよく落とすようにしてください。
(3)食べ残しやゴミを山に捨てない
登山などの際に食べ残しやゴミを山中に捨てた場合、イノシシが誘引されて登山道など人の行動範囲との交差が増え、ウイルス等が人によって運ばれるリスクが高くなります。食べ残しやゴミは必ず持ち帰るようにしてください。
(4)家畜がいる施設には近づかない
野鳥や野生動物などによって運ばれたウイルスは環境中のどこに潜んでいるかわかりません。知らず知らずのうちに靴底にウイルスが付着している可能性もあるため、家畜がいる施設にはなるべく近づかないようにしてください。もし農場に入る場合には、車両の消毒や靴の履替えなど、農場の指示に従うようにしてください。
今回、伝染病を広げないために心がけていただきたいことを御紹介しました。
これらの点に注意していただくだけでも、養鶏場や養豚場、ひいては日本の畜産業を守ることに繋がります。今後、ニュースなどで家畜の伝染病の発生が報道された際にはぜひ関心を持っていただき、私たちにできる対策を周囲の方にも伝えていただきたいと思います。日々口にしている鶏卵や肉などの畜産物がいつまでも安定して供給できるよう、皆様の御協力をお願いいたします。