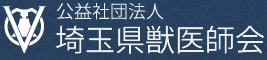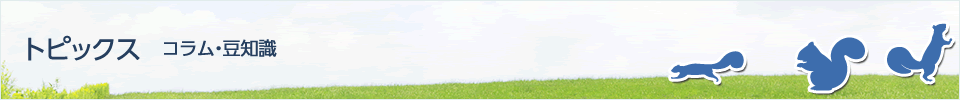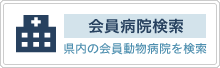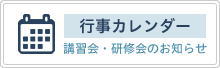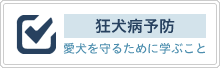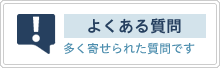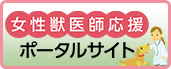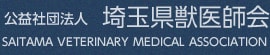はじめに
犬の股関節疾患は多種多様ですが、股異形成はその中でも最も代表的な疾患です。股異形成は数年前まで股関節形成不全といわれることが多かった疾患であり、その名の通り股関節を形成する大腿骨の大腿骨頭と骨盤の寛骨臼のかみ合わせが悪くなり、股関節亜脱臼による骨関節炎を発症します。罹患した犬は特徴的な腰振り歩様(モンローウォーク)、うさぎ跳び歩様などの跛行症状ならびに歩きたがらないといった症状を示します。若齢、中高齢問わず大型~超大型犬種で好発し、痛みで悩む犬は多くいます。股異形成の治療は内科的な保存療法か外科治療の2択になります。今回は現在の獣医療で行われている股異形成の治療方法についてトピックスを書かせていただきます。
1. 内科治療
A) ベジンベトマブ(リブレラ)
リブレラは犬の骨関節炎治療のために開発された画期的な治療薬であり、抗NGFモノクローナル抗体製剤といわれ、痛みに関与する神経成長因子(NGF)の活動を抑える薬です。この薬は1ヶ月の持続的な治療効果を示す注射薬で、副作用も少なく、飼い主さんの投薬負担を減らせるという点でも使い勝手のいい薬で筆者も骨関節炎で悩まれる症例には多用しています。
B) NSAIDs
股関節をはじめとする骨関節炎に対して長年獣医療で使われている薬で、人医療であればロキソニンに似た作用をもつ薬です。この薬の鎮痛効果は非常に高いですが、腎臓への負担や消化管潰瘍や消化管出血の誘発などの副作用があるという点で長期投与に向かないといわれてきました。近年では、長期投与可能な薬、消化管毒性の低い薬が開発されて獣医療でも扱われていますが、それでも副作用が出てしまうケースはあるため、注意が必要です。外科治療を行ったあとの術後鎮痛では第一選択で使われるため、なくてはならない薬であるのは確かです。
C) サプリメント
近年犬用サプリメントは広く普及するようになっており、股異形成に伴う骨関節炎進行予防で筆者もサプリメントを使うことはよくあります。関節軟骨の構成成分であるグルコサミンコンドロイチン、体のあらゆる炎症に対して抗炎症効果を示すω3脂肪酸を含むサプリメントが有効であると考えています。特にω3脂肪酸は体で吸収されて炎症がある部位に直接有効成分が作用するため、股異形成で悩まれる患者さんは若齢、中高齢に関わらず摂取をおすすめしたいです。
D) その他
減量やリハビリも大切です。股異形成の痛みの悪化要因に過体重があります。過体重の犬は他の治療と並行しながら減量を必ずすすめています。リハビリ技術は日々進歩していますが、特に有効といわれるのは水中トレッドミルやプールなどの水を使った運動です。行える施設は限られますが、後肢の筋力トレーニングとしてはかなり効果があると考えられています。
2. 外科治療
A) 人工股関節全置換術(Total Hip Replacement:THR)
股異形成に対する治療で唯一、正常な股関節の動きに近づけることができる方法がこの手術です。この手術は特殊なインプラントを組み合わせて人工的に股関節を作り出す手術で、寛骨臼の役割をするCup、大腿骨頭の役割をするHead、大腿骨の役割をするStemの3つのパーツからなります。この手術は人医療で実施されているものを犬に応用したものであり、繊細かつ難易度の高い手術で高度な技術を要するため、日本国内でこの手術を施術できる獣医師はほんの一握りです。また、インプラントの費用が非常に高価なため施術費用も高価です。しかし、この手術が成功すれば、正常な股関節と同等の機能を得て、元気よく走ることができるようになります。術後は安静が必要ですが、術後1ヶ月もすれば跛行なく、スタスタ歩けるし、次第に走れるようになります。高価な手術であるのに加え、施術後の合併症発症率は10%と成功率100%の手術ではありませんが、成功後の飼い主さんの満足度と喜びは大きく、夢のある手術であると筆者は感じています。
B) 大腿骨頭切除術(Femoral Neck and Head Osteotomy:FHO)
この手術は股関節を形成する大腿骨頭を切除することで、骨の擦れ合いをなくして痛みをなくす手術です。切除した大腿骨頭の代わりに周囲の筋肉や関節包といった軟部組織が関節を埋め合わせて偽関節という新たな関節を作ることで犬は痛みなく歩けるようになります。偽関節が安定するまでに3-6ヶ月かかるといわれているため、術後は跛行が残ることが多いです。関節や筋肉のマッサージなどのリハビリをいかに頑張れるかで術後の筋肉量減少を抑えることができます。手技は簡便ですし、筋肉量が減ってしまっても偽関節が安定すれば走れるようにもなるため、筆者は非常にいい治療方法であると考えています。
C) 二点骨盤骨切り術(Double Pelvic Osteotomy:DPO)
8ヵ月齢までの基本的には大型~超大型犬で骨関節炎のない股異形成と診断された場合適応となっている手技です。骨盤をわざと骨折させて変形させることで寛骨臼が大腿骨頭を覆う面積を増やし、股関節に直接触れることなく正常な股関節に近づけることができます。成長期の犬に施術して変形矯正を行う必要があるため、8ヵ月齢までの施術と限定されています。股異形成の早期診断ができれば適応となる患者さんは増えます。
D) 幼齢期恥骨結合癒合術(Juvenile Pubic Symphysiodesis:JPS)
4ヶ月までに股異形成と診断された場合に適応となる手技です。骨盤の恥骨結合部の成長板を電気メスで焼烙することで成長とともに骨盤を変形させ、寛骨臼が大腿骨頭を覆う面積を大きくすることができます。股異形成は幼齢でも診断されることがあります。例えば、ワクチン接種をしに来た際に触診にて股関節痛があることがわかりレントゲンを撮ってみたら股関節がすでに亜脱臼の状態となっており、診断をされることがあります。獣医師のみなさんは幼齢期の大型犬が来院したらぜひ股関節の触診を行ってみてください。早期に診断し、股異形成で悩まれる症例を減らすことができるかもしれません。
さいごに
股異形成による痛みで苦しむ犬は身の回りに多くいると思います。飼い主さんは自分の犬の歩き方がおかしいと思ったら気軽に動物病院に相談しに行くことをおすすめします。中高齢の股関節痛は早期に治療できなかった場合に生じます。この股関節痛は生涯ずっと続いてしまいます。また、股異形成は膝の疾患と併発して複雑な病態となっていることもあります。股異形成は早期に正しく診断し、適切な治療を行うことが望まれます。